あなたの一番大切な人を思い浮かべてください。
Think of someone you care about.
その人の、好きな食べ物はなんですか?
What is their favorite food?
その人に、どんなものを食べさせてあげたいですか?
What would you like to feed that person?
誰かの「食べたい」を支える介護食を私たちはつくります。
We create caregiving food that supports someone’s desire to eat.
食を五感で楽しむ。
「食べること」は単なる栄養補給ではありません。

料理の美しい盛りつけを「見る」

出来立ての料理を「香る」

調理の音や、食卓の声を「聴く」

食感を確かめながら「噛む」

味の奥深さを「味わう」

料理の美しい盛りつけを
「見る」

食欲をそそる香りを
「香る」

調理の音や咀嚼のリズムを
「聴く」

食感を確かめながら
「噛む」

味の奥深さを
「味わう」
食は人生の楽しみであり、多くの人がその時間を大切にしています。
こうした五感を通じた体験が、食べることを単なる栄養補給以上のものにし、心までも豊かにしてくれるのです。
食は人生の楽しみであり、多くの人がその時間を大切にしています。
こうした五感を通じた体験が、食べることを単なる栄養補給以上のものにし、心までも豊かにしてくれるのです。
食べる喜びをいつまでも。
高齢になると、身体の変化により
食事の楽しみ方が変わっていきます。
高齢になると、身体の変化により食事の楽しみ方が変わっていきます。
食べる力
歯の衰えや義歯の使用(咀嚼力の低下)
飲み込む力の衰え(嚥下機能の低下)
唾液の減少による飲み込みにくさ
味覚
味を感じにくくなる
濃い味を好む傾向になるが、健康面で塩分、糖分の制限が必要になることも
味覚の衰えにより、食欲が減退する
栄養バランス
食が細くなり、必要な栄養が摂りにくくなる
筋力低下(サルコペニア)を防ぐため、たんぱく質の摂取量が重要になる
味を感じるために、亜鉛や鉄を積極的に摂取する必要がある
調理の違い
より徹底した衛生管理
食べやすい食材選び、調理の工夫が必要
味付けや献立の変化がつけにくい
安全性重視で見た目は二の次だったこれまでの介護食。
私たちの目指す介護食は、見た目も味も進化しています。
例えば、さばの煮付けでも…

両方同じ「さばの煮付け」です。
栄養よりも「消化しやすいこと」が重視されていた戦前〜戦後。
そこから病院食やレトルト化が進化するも、味は薄めで見た目も単調なものが多く、「食べる楽しみ」という観点はまだまだ発展途上でした。
1990年代以降介護食の概念が変化し、「食事を楽しむ」ことが重視されるようになってから、見た目の美しさや味のバリエーションが向上し、和食だけでなく洋食・中華などの選択肢が増えました。
近年では、ムース食やゲル化技術を活用し、「見た目は普通の食事なのに、やわらかい」 という商品が増えています。例えば、肉や魚の形を再現したやわらか食品や、ソースやスパイスを活用した味付けの多様化が進んでいます。また、冷凍技術の進歩で、風味を損なわずに提供できる製品も増えてきました。
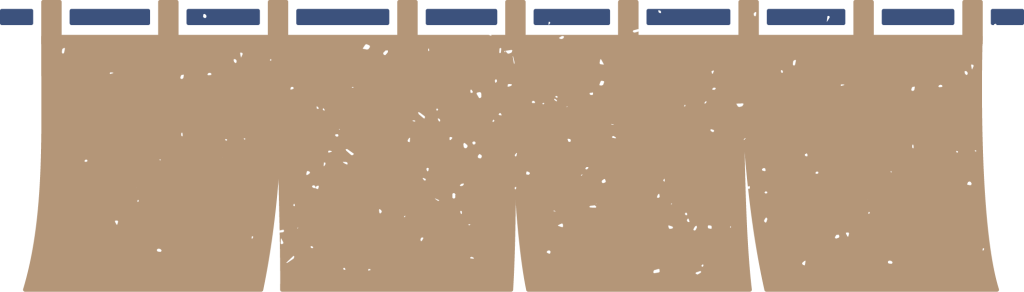

ブースでのご試食メニュー

やわらぎ亭 ビーフステーキ
株式会社ナコム 代表取締役
西村直晃からのコメント
株式会社ナコム 代表取締役
西村直晃からのコメント
なぜ介護食を作ろうと思いましたか?
ある日見た、施設で暮らす身内の食事が忘れられませんでした。お世辞にも美味しくは見えなかったし、食べるのも辛そうでした。食事は単なる栄養補給ではなく、心を満たす大切な時間だと思っていますが、父の食事はその役割を果たしていないように感じました。
それがきっかけで、誰もが安心して、そして楽しんで食べられる食事を作りたいという想いが芽生えました。特に介護が必要な方々にとって、食事はただの義務ではなく、喜びを感じるひとときであってほしい。美味しさと栄養、そして見た目にもこだわった介護食を提供することで、食事の時間がもっと特別なものになるようにと考えています。
介護食として「ビーフステーキ」を選んだ理由は?
ごちそうの代表的なメニューであるビーフステーキ。ですが、噛む力と飲み込む力が弱いという理由で、本当は食べたい熱々のステーキを諦めた方もいらっしゃると思います。ステーキは特別な日の食卓を彩る料理であり、『食べたい』という気持ちが強くあるからこそ、その喜びを届けたいと考えました。
食事は単に栄養を摂るだけではなく、心を満たし、思い出をつくる大切な時間です。家族や友人と囲む食卓で、自分だけ別のメニューではなく、みんなと同じ料理を楽しむことができたら。そのひとときをもっと豊かにできるのではないか。そんな想いから、見た目や香り、ジューシーさにこだわりながら、噛む力や飲み込む力に不安がある方でも安心して味わえるやわらかいステーキを開発しました。
食べる喜びを諦めないでほしい。そんな想いを込めたステーキで、誰もが笑顔になれる食卓をつくるお手伝いができればと思っています。
私たちが作る介護食の未来について
「私たちが創る、未来の介護食」
食べることは、生きることそのものです。 しかし、高齢になり、噛む力や飲み込む力が衰えると、食事の楽しみはどうしても制限されてしまいます。 介護食は、その「制限」を取り払うための手段であるべきだと私たちは考えています。
未来の介護食は、単に「やわらかい」「食べやすい」といった機能性を追求するだけではなく、「食べる喜び」「選ぶ楽しさ」「五感で感じる豊かさ」を大切にするものになるでしょう。 それは、高齢になっても、自分の好きなものを、自分の意思で、美味しく楽しめる食事。 そして、介護をする側にとっても、負担ではなく「一緒に楽しめる時間」をつくるものです。
今、私たちが万博で試食として提供するステーキは、その未来の第一歩です。 ステーキといえば「噛みしめる楽しさ」がある食べ物ですが、通常の介護食では難しいとされてきました。 私たちは、「噛めるけれど、噛まなくても食べられる」という新しい技術で、この壁を超えようとしています。 これは単なる一つの商品ではなく、「食の選択肢を広げることができる」というメッセージでもあります。
介護食は、特別な食事ではなく、誰もが楽しめる「もうひとつの選択肢」になるべきです。 高齢者だけでなく、噛む力が弱い子どもや、病気・障がいを持つ方、あるいは健康を意識するすべての人にとっても、新たな価値を生み出せるはずです。 私たちは、これからも「未来の介護食」の可能性を探りながら、誰もが食の楽しみを諦めなくていい社会を目指して挑戦し続けます。
食べることを、あきらめない。
それが、私たちが創る未来の介護食です。

1946年創業の老舗お好み焼専門店
BOTEJYU®︎Group監修
やわらぎ亭 お好み焼き
BOTEJYU®︎Group 代表取締役
栗田 英人様からのコメント
BOTEJYU®︎Group
代表取締役
栗田 英人様からのコメント
今回の弊社への監修について、どのような想いで引き受けてくださいましたか?
「最幸のやわらぎ」というブランド名およびブランドの提供価値に共感し監修を引き受けることにしました。
嚥下食を通じて幸せを届けたいという御社の願いが込められていると感じました。
そこに私たちのお好み焼の技術と品質を加えることで、笑顔という「最幸」な瞬間を共に生み出したいと考えました。
大阪生まれの「最幸のやわらぎ」とぼてぢゅう®︎のコラボレーション。
これにより関西のソウルフードであるお好み焼をより多くの人の希望に変えていけたら幸いです。
栗田様からみた、今回の介護食お好み焼きのポイントは?
本物のお好み焼を味わってほしいという思いから、長年受け継いできた味を可能な限り再現しました。
いちばんこだわったのは、ぼてぢゅう®︎のおいしさにつながる、特製ソースと白いマヨネーズの配合比率です。
何度も配合を変え、試作することで、納得のいく調和を生み出したと自負しています。
ご自身の経験談も含め、今後の介護食への想いについて
私は55歳のとき、末梢神経の障害により四肢全廃、つまり植物人間になったのです。そこで、器官切開の手術をし、肺の手術をし、しばらく人工呼吸器で延命治療を受けました。
しかし、半年後、奇跡的に自らの肺で呼吸できるようになりました。
入院から7か月目に介護は伴うものの、口から食事ができるようになり、嚥下食を食べ始めました。生きるためと捉えて、おいしさが一切感じられないペースト状の嚥下食を懸命に食べました。
その直後からリハビリをはじめ、2年がかりで日常生活を取り戻しました。
そこから、命あることへ感謝し、食べられることの喜びを強く実感するようになりました。
関西の人にとって、お好み焼は家庭の味であり、ぼてぢゅう®︎のお好み焼は食べ慣れたいつもの味です。人によっては、お好み焼に込められた愛情や懐かしさが蘇ることもあるでしょうし、外国人旅行客にとっては、日本滞在中に食べた思い出の味かもしれません。
だからこそ、食べることが困難になったとき、このお好み焼を食べることで最高の幸せを感じて、生きる希望を見出してもらえたら幸いです。
◼︎BOTEJYU Groupについて
1946年にお好み焼専門店として誕生し、世界で170店舗(2025年3月12日現在)を展開する「BOTEJYU Group」は、創業以来79年以上、多くのお客様に支持されてまいりました。
当社発祥のモダン焼やマヨネーズのトッピングは、日本が誇る“粉もの文化”として定着しました。現在はお好み焼などの鉄板焼にとどまることなく、うどん、ラーメン、丼ぶりといった日本食やご当地グルメを国内外に発信しています。これからも地域の想いと歴史を大切にし、日本の食文化を世界中の人々に伝えるべく活動を続けてまいります。
最後に
「食べることに制限があっても、美味しく楽しめる」工夫が広がっています。
これからの高齢化社会では、「制限された食」ではなく「多様な食べ方を楽しめる社会」が求められています。
介護食も進化し、「特別なもの」ではなく「すべての人が楽しめる食事」として広がっていくでしょう。
私たち株式会社ナコムは、これからも、食事をすべての人が楽しめるように、未来の食事をサポートし続けます。
「あなたの一番大切な人を思い浮かべてください。その人の好きな食べ物はなんですか?その人に、どんなものを食べさせてあげたいですか?」
もう一度、考えてみてください。
未来の介護食について考える、ナコムのパートナー
大阪総合保育大学短期大学部 福祉デザインコースの皆さん
私たちは、大阪総合保育大学短期大学部 福祉デザインコースの皆さんと産学連携し、「未来の介護食」について考えています。
学生たちの新しいアイデアと、私たちの知見を掛け合わせることで、これからの介護食のあり方を探求していきます。
未来の介護食が、もっと「おいしく」「楽しく」「やさしく」なるように──。
この取り組みを通じて、より多くの人が「食の喜び」を感じられる未来を創造していきます。
2024.11.25 介護の日のイベント
・イベント内容
施設様にご訪問し、アフタヌーンティーやレクリエーションのご提供
・目的
弊社が準備したやわらかいステーキや食べやすいケーキを、アフタヌーンティーという特別なスタイルで提供することで非日常を味わっていただくとともに、学生さん主催のレクリエーションを通じて、運動やコミュニケーションの機会を創出します。
・参加者の様子や反応
私たちは、大阪総合保育大学短期大学部 福祉デザインコースの皆さんと産学連携し、「未来の介護食」について考えています。
学生たちの新しいアイデアと、私たちの知見を掛け合わせることで、これからの介護食のあり方を探求していきます。
未来の介護食が、もっと「おいしく」「楽しく」「やさしく」なるように──。
この取り組みを通じて、より多くの人が「食の喜び」を感じられる未来を創造していきます。
・成果と気づき
私たちは、大阪総合保育大学短期大学部 福祉デザインコースの皆さんと産学連携し、「未来の介護食」について考えています。
2025.03.05 調理師による講義とデモンストレーション
・講義内容
嚥下食のメリットとデメリットについて、実食しながら学ぶ
◼︎株式会社ナコムについて
業務:
本社所在地:
代表者:
公式ホームページ:
X:
instagram:
Facebook:
食品卸・介護食の開発〜販売などの、食のプロデュース
大阪府東大阪市加納5-2-8
代表取締役社長 西村 直晃
業務:
本社所在地:
代表者:
公式ホームページ:
X:
instagram:
Facebook:
食品卸・介護食の開発〜販売などの、食のプロデュース
大阪府東大阪市加納5-2-8
代表取締役社長 西村 直晃
